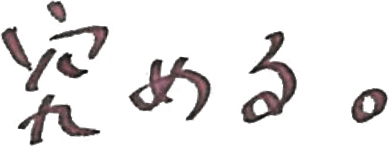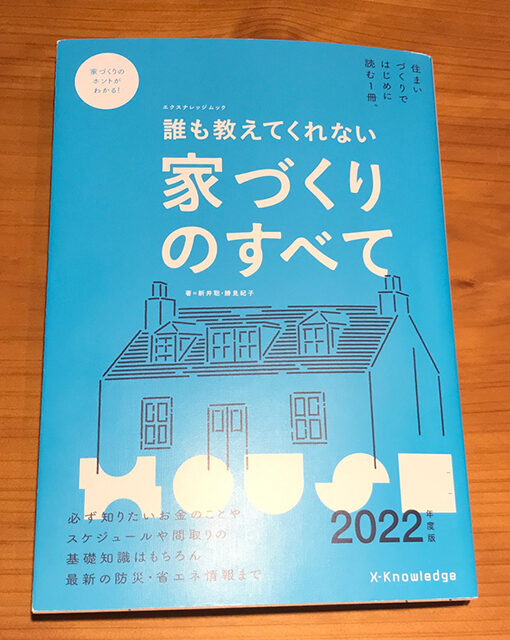なぜ「伐採からはじめる家づくり」なのか
新築、リノベーションに関わらず、私たちがお勧めしているのは、「伐採見学からはじめる家づくり」です。
伐採見学会では、先人たちが50年60年以上かけて大切に育ててきた木の命をいただき、大黒柱や梁、床板などに利用される木が伐採されるのを見学します。澄んだ空気の森の中で、何十年もかけて大きくなった木が倒れる時の体の芯まで響く音と振動は、何とも言えず厳かな気持ちにさせてくれます。
立木は伐採されて命を絶たれますが、製材され大工さんによって家の中で第2の命を吹き込まれ、住まい手を見守ります。そんな過程を見て感じていただく。―それは、単に「家を買う」では味わえないことです。