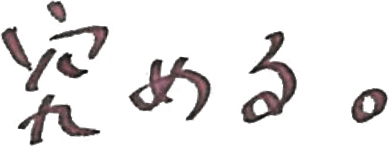床材の選び方とお手入れ方法
住まいは長い時間を過ごす場所だからこそ、目や手など身体に触れる素材が大切です。特に、足が触れる床材には気をつけています。色や質感だけでなく、耐久性、耐水性などそれぞれの特性を意識して使い分けています。天然の木材をそのまま使用したフローリングの事です。複合フローリングとは異なり、1枚の木から切り出された材料を使っているため、木目や色合いが1枚1枚異なり、自然な風合いと質感が楽しめます。木の種類により色や質感が異なるため、実物を見ながら選ぶのをお勧めします。また、熱伝導率が低く冬場でも冷えにくかったり、調湿作用もあります。:比較的柔らかいためクッション性があり、長時間立っていても疲れにくく、足に優しい樹種です。時間が経つにつれて飴色に変化していきます。温かい感触の反面、柔らかいので傷がつきやすくもあります。:初めは白っぽい色合いですが、時間が経つにつれて飴色に変化し、味わい深い風合いになります。香りが良く油分も含んでいるので腐りにくく、杉よりもキズがつきにくい樹種です。:節が少なく、はっきりとした力強い木目が特徴です。また、広葉樹の中でも特に硬い木材で、傷や凹みに強い樹種です。普段は掃除機でホコリを取り、水拭きは避け、米の研ぎ汁を加えた水で固く絞った布で拭くと木のカサつきを防げます。落ちにくい汚れは、固く絞った雑巾で拭き、仕上げに乾拭きで水気を取るとよいでしょう。塗装は撥水性がなくなり水が染込むようになったら再塗装の時期です。1〜2年に1回が目安です。水廻りは早めに再塗装をして下さい。