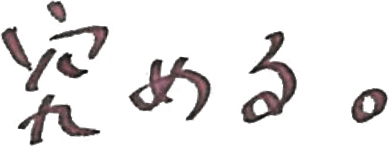断熱や空調 時代の変移と今の家
私が修行した設計事務所は職人の手による家づくりを目指していました。家が新建材と工業化へ向かう時代に対して自然素材や人との関係から生み出される家づくり、モノづくりを大切にしようと。 玄関ドアや窓は建具職人による手造り。木の建具は風格があって味わいが増します。
所長の考えは「高気密高断熱は自然ではない。」「エアコンは無粋だ。」「風の通り道を考え夏はカヤを吊って過ごすといい。」(いっとき事務所でカヤの販売手伝いもしていたくらい) 20年以上前は今ほど暑くなく、断熱や気密も今ほど注目されていませんでした。
しかし今は連日の猛暑に熱帯夜 とてもじゃないけどカヤで快眠は難しいでしょう。断熱と気密への意識が高まると同時に知識や技術もあがりました。世間も性能を求めるようになりました。 住まいは時代を写します。自然の力だけで心地よく過ごすのは難しくなりつつありますし 我慢を良しとする時代でもありません。健康的な住環境を考えると断熱、気密の性能を上げていくこと エアコンなどの設備に頼る事も大切です。
採光や庇といった昔からの知恵も使って出来るだけ省エネにしながら、新しい技術や機械も採用するバランスが求められます。ただし、気をつけたいのが性能と経済性だけにとらわれると住まいがどこか息苦しい。ビニルハウス、冷蔵庫の中のように感じてしまうのでしょうか?それに情緒がないというか。
家づくりをする上でどこか自然を感じられるようにしたい思います。
軸足は自然とともに
天空の城ラピュタで「土から離れては生きられないのよ」という名台詞があります。
家もまた「自然と切り離された住まいは息が詰まるのよ」と感じています。